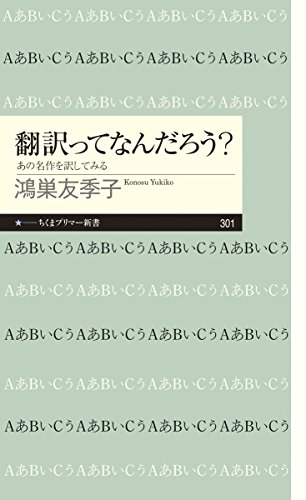最近のようす
1歳を目前にして子どもが保育園に通い始め、お約束どおり貰ってきた風邪をわたしも頂戴した。ありがたくない。わたしは粘膜がよわいくせにカレーやコーヒーが好きで、慣らし保育中に調子に乗ってカレーランチやカフェをめぐっていたせいで風邪のついでに喉を傷め、4月はほとんどずっとひどい咳が止まらなかった。新型コロナ陽性ではなかったけれど、咳込んでいると外にも出かけづらく、体力も奪われて家でゴロゴロと寝てしまい、育休明け前の貴重な自由時間がもったいなかったな~。まあ、1年ぶりにゆっくりできたということで良しとしましょう。春の陽光を窓の外にながめながら怠い身体をソファに横たえていると、ちょうど1年前の臨月のころを思い出してなつかしかった。
ウィラ・キャザー『マイ・アントニーア』
体験したことはないのに本能的に感じる、アメリカ開拓時代の大平原での農業生活への郷愁。怠惰な現代社会に慣れきったわたし自身にはきっと耐えられないと、わかっていても感じるあこがれ。
幼少期に喪った尊敬すべき父から、心の遺産とでもいうような精神を受け継ぎ、アントニーアは人生の苦難や紆余曲折に出会っても「命の炎」を絶やすことなく自分の生きるべき場所で「生命の爆発」を産みだした。
面白いと思ったのは、そういう女の一代記が幼馴染の男の視点で、彼の人生を通して見た姿として描かれていること。この「他者の目を通した語り」は『グレート・ギャツビー』に影響を与えたとフィッツジェラルド本人が認めているそうだが、特に女の人生を異性の目から描いている、それもファムファタールや恋愛対象としてではなく、ひとりの人間として、というところが特別だなと思う。
全体としてアントニーアの活力に満ちた姿は肯定的に描かれてはいるものの、その満ち足りた家庭を支える陰として、望んだものとは違う人生を送る彼女の夫が少しの哀愁を帯びた姿で登場している。そしてアントニーアと全く対照的で、都会で成功し自立した女として描かれている青春時代の女友達たち。特にリーナ・リンガードという女のエピソードはまるまる1パートを割いて、語り手ジムと恋愛関係にあったことが示唆されている。
ジムは「アントニーアを語ることは自分の人生を語ること」とまで言っているのにもかかわらず、恋に落ちるのはアントニーアではない。このことは、深い関わりを持った2人の人間が異性であった場合は、恋愛とか結婚に着地しなければならない、という大きな流れへの反抗みたいなものなのではないか? アントニーアとジムはお互いの生涯にとって最も重要な存在であった。にもかかわらず…というより、そうであるからこそ、彼らの関係は性別を超えた何ものかでしか有り得なかった、と思うのだ。
倉本 一宏『はじめての日本古代史』
ずっと気になりつつも出会えていなかった日本古代史の通史本。根拠のない断定や逸話レベルの紹介は避け匂わせる程度に留めているのが、もう一歩知りたいという気持ちにさせられる(おそらくそれが著者のねらい)。
奈良時代の陰謀にまみれた政権交代劇が面白すぎて、ドラマか小説かを読みたいと思ってしまった。奈良時代にも孤独な独裁者がいたのだ。それに、そもそも天皇制とは何か、後の時代の日本人にとっての天皇や朝鮮半島が精神的にどういう存在であったかという基盤がこの時代に作られた、ということがなんとなく分かった気がする。
鴻巣 友季子『翻訳ってなんだろう?』
翻訳文学に触れる機会が多くなり、訳者がどのような思考の経緯を辿っているのか、原文とどの程度異なるものなのか、気になっていたので読んでみたかった本。翻訳といってもまずはとにかくテキストの中に深く潜り込み、文章の意味するところを読み取ること。そして文体の味わいを消さないまま、日本語に移し替えること。その難しさは個々のケースにより体当たりの作業で、「訳」というよりむしろ「移植」というようなものだと感じる。個人的には今後もありがたく翻訳の恩恵を享受しようと思うものの、英語圏古典文学の原文文体に触れながらの平易な解説も楽しめた。
藤野 可織『ピエタとトランジ <完全版>』
女子高生名探偵〈ピエタ〉とその親友であり語り手の〈トランジ〉。〈ピエタ〉は行く先々で事件に遭遇する特殊体質がゆえに、所属する組織を意図せず次々と壊滅状態に陥らせていく。
短編で読んだときはよくある探偵ものマンガの設定を茶化しているのかなと思ったのだけど、長編になるとその「呪い」が最大の障害になる。たとえ世界中を敵に回しても、世界にたった一人だけは自分の味方がいる、という理想のロマンス。ふたりは女でありながら「産む」ことからもはや自由になり、「別の生を土台」にさえして、むしろ自分たちの破滅の宿命に世界を巻き込んで、2人で生き、2人で死ぬ。
呪いとともに生きることは不自由なようだが、それでも外に出ていくことをやめない〈ピエタ〉。身体を持ちながら生きることの方がむしろグロテスクで、そこからピエタとトランジの2人だけが自由になれた。ファンタジーだからこそ実現できる、「女が女と生きること」の理想を象徴的なかたちで詰め込んだ物語だ。
高殿 円『上流階級 富久丸百貨店外商部』 (小学館文庫)
男性社員ばかりの百貨店外商部に異動になった元敏腕女性バイヤーの鮫島。仕掛けやコネ、使えるものは何でも使って奮闘する姿を描くお仕事エンタメ。気分転換に気楽に読めつつ、春からの新生活に気合いを入れ直した楽しい読書だった。
私自身はこういう自分ならではの人間性を売り物にする仕事をしていないけれど、難しい課題に直面して「さてどうする」と頭を悩ませなんとか踏ん張って切り抜けるような局面ってどこの職場にもあるよね。それにしても、イベントごとに人を招き、正月から外商さんみたいなよその人まで年始の挨拶をしにくるような家業は大変そうだなあ。
野田サトル『ゴールデンカムイ』
単行本の表紙を貼っていますが、ヤンジャンアプリの全話無料で最終話まで読みました。マンガでも小説でも、わたしはあまりリアルタイムで流行っているものを読んだり、積極的にインターネットで他の人の感想を読みに行くという経験がなく、内容以前にそこが結構新鮮な体験だったかも。特にこの作品は、物語とそれが巻き込んでいったものに相当のパワーがあるので、最終話公開後はSNSでどこを見ても感想が転がっているという状況。自分ひとりでは到底気づけなかったことをたくさん気づかせてもらえて楽しかった。一方で、頭の中が他人の感想ばかりになり、最終話をよんで自分自身が何を思ったのかとかいうことがいまひとつよくわからなくなってしまった面も。
ただ単純に、最終話とその直前はものすごく濃い物語をつめこんだ感があり(だからといって語りの丁寧さが損なわれているとも思わせないのが凄さでもあるのだが)、もっとじっくり引き延ばせるものだったのなら何話もかけて読みたかった気がする。これが週刊連載で最終話の掲載日が絶対に変更できないと事前に決まってしまっていたのは、もったいなくもあったんじゃないかなあ。まあ、単行本になるときに相当の加筆・修正があるのではという話だけれど。
一番うーんと思ったのは、最後のオチになっていたシライシが東アジアの王様になっていた、というところ。金貨の絵面はめちゃくちゃ彼らしいのだけど、即座に第二次大戦で日本がやった植民地支配を連想してしまい、笑えなかった。でも、これはシライシもまた旅の中で出会った房太郎の言葉で自分を変化させたいう話なんですよね…。その視点なら、房太郎の呼吸をみていたからこそ水中に落ちた杉元をシライシが助けられた、というところをもっと大きく描いてほしかった(この点こそ、SNSのコメント読まなければわたしは気づけてなかったので…)。
あと、いろいろな感想を見られてよかったと思うのは、わたし自身は和人がアイヌを同化してきた歴史的背景に無頓着なまま読んでしまっていたなあという反省。最終話を読んでそこに対する批判的視点を持てる人がたくさんいるというところにまず感心してしまった。ただ、わたしのような「知識もなく、積極的に知ろうという意欲もなかった」という人間に、アイヌの言葉や考え方を身近に感じさせ関心をいだかせる、「知らねば」と思わせる力のある作品であるのは、やっぱりすごいよ。